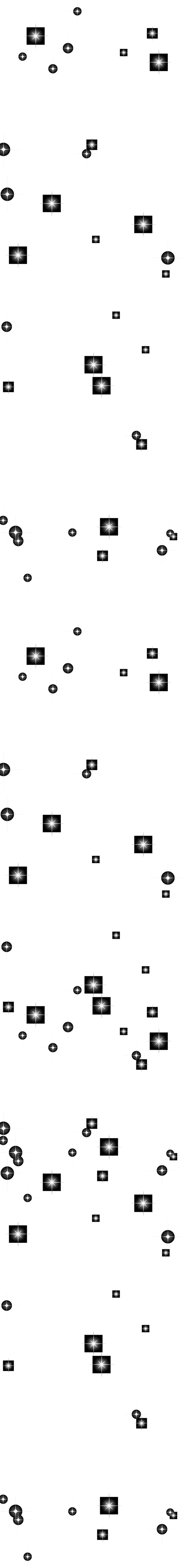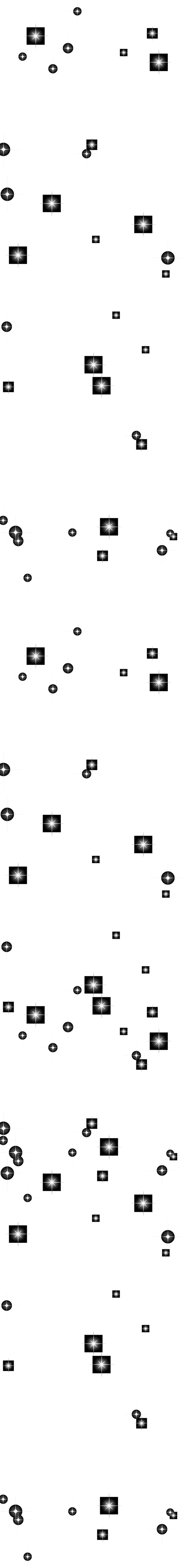
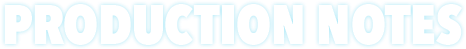


- 「イタズラなKiss」はこれまでに、日本ドラマ(1996・2013)、台湾ドラマ(2005・2007)、韓国ドラマ(2010)の映像化に加え、アニメーションや舞台さまざまなジャンルで漫画の世界を表現してきた。そして、ついに初の映画化が実現! 過去にも映画化の話は何度となく浮上したものの、原作者の急逝により物語が未刊であることや、原作を大きく変更することなく23巻のエピソードのどこをピックアップするかなど、映画の脚本は苦戦が強いられてきた。今回、脚本を担当するのは溝口稔監督。多田氏と家族ぐるみの交流のあった溝口監督は、彼女の亡き後「イタキス」の著作権を管理しながらドラマ化、舞台化、アニメ化に携わってきたこともあり、映画の監督&脚本はまさに適任。
また、ファンの熱い想いが映画化へと突き動かした。連載開始から26年経った今でも「イタキスを終わらせないでほしい!」という声の多さ─現在、上は80代から下は小学生低学年まで、幅広い年齢層のファンがいる。溝口監督は「イタキスは、年齢も性別も国も超えるスタンダートな作品」と語る。原作を大切にしながらその魅力を最大限に活かすために、今回の映画化で用意したコンセプトは“時代に左右されるものは描かない”ことだった。現代では当たり前の携帯電話やスマホ、SNSを登場させることなく、普遍的な青春ラブコメ映画にしてアットホームな家族映画を完成させた。


- 映画版はシリーズで展開。琴子と入江直樹のキス─卒業式のキス、清里でのキス、プロポーズのキス、ファンからの人気が最も高いキスのエピソードを中心に描いていく。2人のキスに物語の軸を絞ったとはいえ、ドラマ版ではプロポーズのキスまでに16話かけていることからも、原作を逸脱することなくまとめるのはウルトラ級の難技。しかもコミックでは描かれていないプロットを取り入れているのは、多田氏と親しかった溝口監督だからこそ成し得たアイデアだ。たとえば、琴子が入江直樹の部屋から黙ってノートを借りるシーンは、連載時の次号予告で多田氏は「停電の夜の事件以来……」というようなキャッチを書いていたが、掲載時には停電のエピソードはなかった。「きっと描きながら他のアイデアがパッと浮かんで忘れたんでしょう(笑)。なので、映画のなかで停電を復活させました」。映画ならではのシーンがシリーズでも描かれる予定だ。


- 佐藤寛太(劇団EXILE)は「直接会った瞬間に、彼こそ入江直樹だ!とピンときた」、美沙玲奈は「写真を見て、このキュートな笑顔はまさに琴子だ!」と、どちらのキャスティングも難航することなく「舞い降りてきてくれた」と溝口監督。とはいっても、絶大な人気を誇る原作の核となる主役の2人を演じるのは容易いことではなく─佐藤と美沙はクランクイン前に2人の距離感や掛け合いを身体に染み込ませるため、入念なリハーサルを行い、撮影に臨んだ。
入江直樹を演じる難しさは、感情を表に出さないキャラクターを目の動きと視線で表現すること。具体的に「頭の悪い女は嫌いだ」というセリフで監督が求めた“目”は「氷山のような冷たさ」というように。そんなクールな男が、幼い頃の女装写真を琴子から見せられた時は、何とも言えないびっくりした表情を見せる。琴子の言動によって入江直樹の感情のスイッチが入るわけだが、その一瞬の感情を表現するのは「相当難しかったはず」だと言う。なんでもこなす完璧で天才な入江直樹にとって、唯一の想定外は琴子そのもの。そんな琴子を演じるために必要だったこと、美沙に求められたのは、何はさておき「元気」であることだった。というのも琴子はファンにとっては等身大のキャラクター。勉強で行き詰まったときは、琴子だって頑張って国家試験に受かってナースになれたんだから! と元気をもらう、仕事で疲れたときは、琴子の明るさと前向きさでホッとさせられ元気をもらう……どんな時も元気を届けるキャラクター琴子を美沙はみごとに体現してみせた。サブキャラクターに関しても、原作に限りなく忠実な金之助、じんこ、理美がスクリーンに映し出される。
根っからの悪人は登場しないこと、友情・愛情・家族愛、さまざまな愛が詰まっていることも「イタキス」らしさだ。その世界観には、原作者のリアルな生活が漫画の世界に投影されている。琴子と入江直樹の恋路で重要な役割を果たしているのが、お茶目でキテレツな入江ママだ。自分の息子よりも琴子ラブ! なキャラクターだが、実は多田氏の義理のお母さんがモデルなのだそう。もちろん漫画として脚色はされているが、身近な人がモデルになっているからこそより温かみのあるキャラクターたちが生まれていったのかもしれない。